この記事では、就活生にとっての永遠のテーマ「大手企業がいいのか、ベンチャー企業がいいのか」の答えを紹介します。
なお、この記事を書いている僕は、
- 新卒で3,000人規模の大企業に就職
- 転職1回目で30人規模のベンチャーに入社
- 転職2回目で再度大企業(メガベンチャー)に入社
という経歴を持っています。
結論としては、新卒でベンチャーに就職するのは辞めておいたほうが良いです。30人規模のベンチャーでは採用担当もしていた僕が言っていいのか分かりませんが(汗)。
代わりにおすすめするのはメガベンチャーに就職することです。実は、メガベンチャーは大企業とベンチャーのいいとこ取りができるのです。
「大企業かベンチャーか」という2択に縛られる必要はありません。
ただ、大企業とベンチャーのどちらが自分に向いているのかを知りたい人のためにも、大企業とベンチャー企業の特徴やメリット・デメリットを対比させながら、
- ベンチャー企業をおすすめしない理由
- それでもベンチャーに入社したほうがいい人
- メガベンチャーとは?
- メガベンチャーの選考を突破しやすくする方法
を紹介していきます。
ベンチャーと大企業の違い

大企業とベンチャーの特徴を大まかに比較すると以下のようになります。
| 項目 | 大企業 | ベンチャー |
|---|---|---|
| 仕事のスピード感 | 社内りん議や意思決定 機関が多数あるため遅い | 組織の階層が少ない分、 現場判断で動くことが 多いので早い |
| 社内の雰囲気 | 年齢層が高い人が多くなる ので落ち着いた雰囲気 | 年齢層が若いので、 エネルギッシュ |
| 身につくスキル | 特定のスキルを身につける のに向いている | 何でも屋さんになる |
| 給料・福利厚生 | 新卒だと給料は低めだが 福利厚生含めて良い | 基本的には高くはない |
| 昇給・昇格 | なんだかんだ年功序列 | 結果さえ出せば 昇給・昇格しやすい |
| 社会への影響力 | 資本力と既に業界との太い パイプがあるので大きい | 特定の業界のニッチな市場を 攻めているため小さい |
メガベンチャーの場合は、以下のような感じです。
- 仕事のスピード感
⇒ 大企業よりは階層が浅いが、上司の判断を仰ぐ必要があることが多く少し遅い - 社内の雰囲気
⇒ 平均年齢は20~30代前半でやや落ち着いている - 身につくスキル
⇒ 特定のスキルを身につけることに集中できる - 給料・福利厚生
⇒ 給料は高め。福利厚生は大企業ほど充実してない - 昇給・昇格
⇒ 結果を出しても昇給するとは限らない。上司や周りで働いている人の評価も大事 - 社会への影響力
⇒ サービスの知名度もあるので、影響力もそこそこ大きい
メガベンチャーといっても様々な会社があるので一概に言えないこともありますが、本当に大企業とベンチャーの中間みたいな感じです。
ここからはもう少し詳しく大企業とベンチャーの違いについて紹介していきますが、メガベンチャーについて知りたい人はメガベンチャーとは?に飛んでください。
大企業のメリットとデメリット

まずは大企業のメリットとデメリットを紹介します。
- 【◯】優秀な人が多い
- 【◯】自分の伸ばしたいスキルを伸ばしやすい
- 【✕】事業全体を俯瞰する目線は持ちにくい
- 【✕】昇進までに時間がかかる
【◯】優秀な人が多い
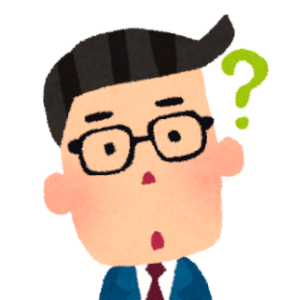
ベンチャーの方が若くて優秀な人が多いのでは?
と思った方はたぶん少し偏見があります。
確かにベンチャーが集まる就活イベントでは優秀な若手社員がプレゼンしていますが、それは全社員のうちの一部。
そもそも就活のときの競争率は大企業のほうが高いので、大企業のほうが優秀な人を採用しやすいです。
また、単純な確率の問題で、「大企業 = 社員数が多い = 優秀な人も多い」とも言えます。
【◯】自分の伸ばしたいスキルを伸ばしやすい
これも意外かも知れませんが、「このスキルを身に付けたい!」と思ったら大企業の方が適しています。
大企業だと仕事が細分化されて複数人に割り振られているので、営業スキルを身に付けたい人は営業だけに専念できるし、アプリのデザインを極めたい人はそれだけを基本的にはやり続けることができます。
では、次にデメリットを見てみます。
【✕】事業全体を俯瞰する目線は持ちにくい
仕事が細分化されていることで、全体像を把握するのは難易度が上がります。
毎日「とにかく新規の契約を取ってこい!」とだけ言われていても、「結局この事業全体では儲かっているのか」「そもそもこのサービスにはこんな機能がついていた方がいいんじゃないか」などのトピックは見えてきません。
【✕】昇進までに時間がかかる
大企業だと昇級ルールがきっちり定められている会社が多く、ベンチャーよりも昇進までの時間が長くかかりがちです。
就活人気ランキング上位の大手企業では未だに年功序列の色合いが強く、どれだけ優秀でもマネージャーになれるのは10年目以降、とかが決まっていたりします。
ベンチャーのメリットとデメリット

次にベンチャーについて見ていきます。まとめるとメリットとデメリットはそれぞれ以下の3点ずつです。
- 【◯】優秀な人と近い距離で働ける
- 【◯】若い年次から経営全体に関わる視点をもちやすい
- 【◯】働けば働くほど若い年次でも昇格できる
- 【✕】何でも屋さんになってしまう
- 【✕】人の入れ替わりが早く、優秀な人がどんどん抜けていく
- 【✕】常に自分で自分を追い込む環境を作らないとヒマになる
【◯】優秀な人と近い距離で働ける
ベンチャーは幹部クラスは優秀な人が多く、彼らの仕事のスタンス・物事の捉え方を直接会話して影響を受けられるのは最大のメリットです。
ベンチャー在籍時の経営ボードMTGでは、自分より数段高い次元で物事を捉えていることに刺激を受けましたし、それで自分も大きく成長できました。
【◯】若い年次から経営全体に関わる視点をもちやすい
自分が担当する業務の幅が広いと、その分仕事全体の流れをみる視点が養われるのも利点です。
商品企画〜売上計画立案〜販売〜入金管理までを経験すると、商売の一連の流れを経験できることになります。
【◯】働けば働くほど若い年次でも昇格できる
優秀な人材を上の役職に登用するスピードはベンチャーならではです。
将来自分で起業したい、若いうちに自分に負荷をかけて成長したい、と思っている優秀な人材をつなぎとめるために、成果を残したらより高度な仕事をどんどん任せていきます。
では次にデメリットを見てみましょう。
【✕】何でも屋さんになってしまう
人手不足から一人何役もこなす必要があるので、必然的に1つの事に対して割ける時間は限られます。
なので、「専門性を築くスピード」という観点では大企業には劣ります。
特に20~30代ぐらいだと専門性が高いほうが市場価値も高くなりやすいので、器用貧乏になってしまうリスクがあることは理解しておくべきです。
更に、ベンチャーでは「俺の担当はここまで」という姿勢は最も嫌われる考え方の一つなので、役割を超えて「会社のためなら担当外だがこの仕事をやる」というスタンスが求められること頭に入れておきましょう。
【✕】人の入れ替わりが早く、優秀な人がどんどん抜けていく
そもそも3年以内にほとんどが潰れていくベンチャーに、定年まで勤め上げるという考えはありません。
優秀な人ほど他の会社からのオファーもありますし、自分をステップアップさせたいという意欲が強いので、2,3年で主要メンバーが総がわりということもザラにあります。

新卒採用をした時に憧れていた先輩が、入社したら退職していた。詐欺だ!
という学生が毎年いますが。。。ベンチャーはそういうものです。
【✕】常に自分で自分を追い込む環境を作らないとヒマになる
ベンチャー企業は常に忙しい!と思っていると見誤ります。
ベンチャーでは決められた定型の仕事はあまりなく、自分が会社にとって必要だと思ったこと、クライアントにとって価値があると思ったことはどんどん実行していくことが求められます。
つまり、自分で仕事を作りだしていかないと、誰かが与えてくれるわけではないので、単純に暇です。
以上をまとめます。
- 大企業には優秀な人が多く、成長しやすい環境がある一方、昇進には時間がかかる
- ベンチャーでは昇進は早い一方、成長環境が整っておらず、特定のスキルも身につきづらい
すでに特定のスキル(プログラミングなど)を習得しているのであれば、新卒でベンチャーに行くのもありかもしれません。
しかしそうでないのであれば、基本的には大企業に入社することをオススメします。そうした方が、実は早く成長できるんですね。
» ベンチャーなら成長できるってほんと?を考察した
なぜ新卒でベンチャーに行くべきではないのか?

ベンチャーをおすすめしない理由を、具体例を交えて説明します。
スキルもないのにベンチャーに就職すると悲惨
これは一例に過ぎませんが、前職のベンチャー企業で起きたことを紹介します。
新卒で入った子で「事業責任者やりたいです」と言っていた子がいたのですが、1ヶ月経っても何もできてませんでした。
本来、事業を大きくするためにやるべきこともたくさんあったのですが、何もしてなかったのです。
彼はサボっていたつもりはないのですが、単純に経験不足で「どう考えていいのかわからなかった」のです。
ベンチャーは教育体制が整っていないので、スキルがないと無駄な時間を過ごすハメになります。
それでもベンチャーに入社したほうがいい人
ただ、特別なスキルがなくてもベンチャーに入社したほうがいい人もいます。
それは以下の3つのどれかに当てはまる人です。
早く起業したい人
「起業したい人がベンチャーに向いている」というよりかは、「起業すると社員としてベンチャーで働くよりも大変なので、ベンチャーに就職してきつさに慣れておくべき」といったほうが正確です。
起業して成功するのは本当に甘くありません。経営者の大変そうな姿を身近に見てたのでよく分かります。
できれば大企業かメガベンチャーで特定のスキルを身につけてからベンチャーに転職したほうがいいのですが、新卒でベンチャーに入社してがむしゃらに働いたほうが結果的に早く起業できるかもしれません。
仕事を通じて明確に達成したいことがある人
解決したい社会課題、実現したい世の中が明確な人は、ベンチャーでの仕事にやりがいを感じられます。
ベンチャー企業が掲げているミッションやビジョンに共感できることが必須ですが、大企業に比べると自分の手で世の中を変えていっている実感を味わいやすいです。

僕は自分の中でビジョンが明確ではなかったので、この点ではモチベーション維持はできませんでした。
自分の実力に自身がある人
ベンチャー企業は基本的に実力主義です。結果を出せば給料は上がります。
給与体系がしっかりしてないのもありますが、結果を出してる人にしっかりと給料を支払わないと辞めていってしまいますからね。
また、先ほども紹介したように昇進もしやすいです。
そのため自分の能力に自信がある人はすぐに会社の中心になれるため、ベンチャー企業に向いています。
詳しくはベンチャーに絶対向かない人と向いている人の違いで紹介してますが、「あ、自分は当てはまる」と思った人はぜひベンチャー企業を受けてみてください。
いいベンチャー企業の探し方や、ベンチャー就活で利用すべき就活サイトは以下の記事にまとめているので、読んでみてください。
メガベンチャーとは?

ここまでの内容を読んで「自分はベンチャーに向いてなさそうだな…」と思った人はメガベンチャーを受けてみましょう。
メガベンチャーとは「大企業とベンチャーの中間みたいな感じ」と紹介しましたが、「新規事業の立ち上げに積極的な大企業」とも表現できます。
具体的にどういう企業があるのかは別の記事にまとめています。
メガベンチャーの入社難易度
ここまでメガベンチャーをおすすめしてきましたが、とはいえ入社するのは簡単ではありません。
- 楽天(68位)
- DeNA(77位)
- サイバーエージェント(169位)
- リクルート(193位)
がランクインしています。
メガベンチャーは採用人数が多いとはいえ、万全の対策をした上で選考に臨みましょう。
メガベンチャーの選考対策

具体的なメガベンチャーの選考対策として、以下の3つを紹介します。
就活エージェントを利用する
就活エージェントとは、就活生1人ひとりに対してアドバイザーがついて就活全般のサポートを無料でやってくれるサービスです。
面接対策はもちろん、ESなどの書類の添削や就活の相談にものってもらえます。
エージェントによっては、就活セミナーや企業の人事や社長と直接話せるイベントを開催してることもあり、イベントにメガベンチャーが来ていることもあります。
また、イベントが選考を兼ねていることもあり、特別な選考フローへと進めることもあります。

これらのサービスが全て無料で利用できるので、就活生なら利用しない理由がありません。
おすすめの就活エージェントも選んでおいたので、紹介します。
- あなたに合った企業を的確に紹介 ⇒ JobSpring Agent
- どんな仕事をやりたいか明確にしたい ⇒ irodasSALON
- 早く内定を獲得したい ⇒ キャリセン
- エンジニア志望 ⇒ レバテックルーキー
- 丁寧なカウンセリング ⇒ キャリアチケット
JobSpring Agent

JobSpring Agentは、マッチング精度の高さがウリの就活エージェントです。
CUBIC適性検査やAIなどのデータに基づいてあなたに合った企業を紹介してくれるため、内定承諾率70%(平均は約36%)の実績を叩き出しています。
大手の就活サイトでは、メールで大量の送られてくることが多い一方で、JobSpring Agentでは平均3~4社ほど。本当にあなたに合う企業のみを紹介してもらえるので、1社1社の選考に集中でき、結果として選考も突破しやすくなっています。
もし選考に落ちてしまっても、不合格理由から改善策を一緒に考えてくれ、内定獲得までつきっきりでサポートしてもらえます。
利用者のアンケートでも「自分の話を親身に聞いてくれるか」で平均4.4点(5段階中)と人気があり面談の枠もすぐに埋まってしまうので、早めに登録しておきましょう。
irodasSALON

irodasSALONは、あなたが本気でやりたいと思える仕事を見つけられる就活エージェントです。
自己分析や企業分析のサポートのために、
- 以前は5万円もしたキャリア講義
- 160ページを超えるキャリア形成教材
などが無料でもらえます。
加えて、キャリアカウンセラーが一人ひとりについてくれるので、困ったことがあればすぐに相談できます。
結果として、
- 利用者の満足度95%
- 年間に13,000人が利用
- 内定率98%
といった実績が生まれ、企業からも信頼されているため、人によっては「irodasSALON特別ルート」で選考を受けられることがあります。
当然、特別ルートは人数制限があるので、早めに登録しておくと有利です。
キャリセン

キャリセンは、内定率の高さや短期での内定獲得に定評のある就活エージェントです。
元人事担当者や有名なキャリアコンサルタントと、1時間のマンツーマン就活相談などを通して内定獲得率が5.4倍になり、年間1,000人以上が内定を獲得しています。
採用担当の本音を熟知しているからこそ達成できた数字ですね。
最短2週間で内定を獲得できるので、就活に出遅れて焦っている人に特におすすめです。
紹介企業の選考に関しては、合否関わらず企業側からのフィードバックをしっかり伝えてくれるので、面接の練習台としての利用価値もあります。
レバテックルーキー
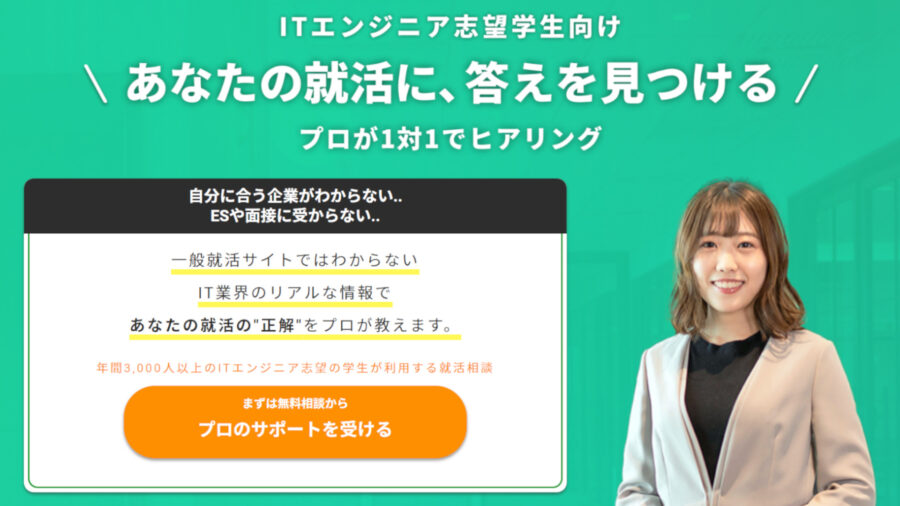
レバテックルーキーは、ITエンジニアになりたい就活生や大学生・院生に特化した就職エージェントです。
エンジニアの転職やフリーランスで日本最大級のエージェントなので、エンジニア業界を熟知しています。
レバテックルーキーの強みをまとめると以下の通りです。
- 利用者の内定率は85%以上
- 大手・中小・ベンチャーの優良企業を紹介してくれる
- 受かるES、GD、面接ノウハウをこっそり伝えてもらえる
- 最短1週間で内定を獲得できる
- 多数のIT企業の人事とつながりがあり、独自の情報もあり
就活アドバイザーがエンジニアの知識に精通しているので、あなたの志向性やスキル、入社後のキャリアパスを考慮したアドバイスもしてもらえます。
人気があるため面談の枠は埋まりやすいので、早めに登録しておきましょう。
キャリアチケット

キャリアチケットは、オリコン顧客満足度ランキングで新卒エージェントとして総合1位を獲得したほど評価が高いエージェントです。
キャリアチケットの強みをまとめると以下の通りです。
- 過去、60,000名の就職支援をしてきたアドバイザーが専任で内定獲得まで個別サポート
- 受かるES、GD、面接ノウハウをこっそり伝えてもらえる(「内定率が1.2倍になる面接対策プログラム」がある)
- ベンチャー向けの面接対策セミナーも実施
- ベンチャーから優良企業まで、幅広い企業を取り扱っている
- 多数の企業の人事とつながりがあるため、特別推薦枠も多数あり
また、キャリアチケットでは就活イベントも開催しています。
ベンチャー志望の学生ならベンチャー向けの面接対策と企業紹介セミナーには参加しておくべきです。
オンラインで実施されており、参加できない学生が出てくるほど人気です。
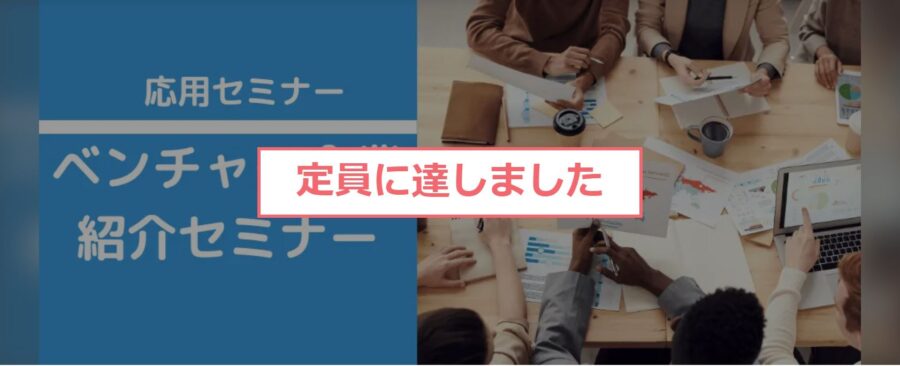
セミナー内では、ベンチャー企業の働き方や選考のポイントも教えてもらえ、セミナー当日にセミナーに参加しているベンチャー企業にも応募できます。
効率的に就活を進めるためにも、ぜひ参加しておきましょう。
他にもベンチャーに強い就活エージェントは以下の記事で紹介しているので、合わせて読んでみてください。
ベンチャーを練習台にする
就活エージェントである程度の選考対策はできるとはいえ、本番となると緊張感も違ってきます。特に面接ではある程度場数を踏んでおくことが重要です。
あまり褒められたことではありませんが、ベンチャーはそもそも受ける人が少なく書類選考がないところもあるので、面接の練習にはもってこいです。
どんなベンチャーを練習台にするべきかや、ベンチャーを練習で受けるときの注意点などを以下の記事にまとめているので、ぜひ読んでみてください。
» 就活でベンチャーは面接練習になる!受けるべき理由と注意点を紹介。
OB・OG訪問をしてちゃんと情報収集をする
OB・OG訪問を行い、先輩社員からネット上にはない情報を聞いておくことも有効です。
選考の内容や面接でどんなことを聞かれたかなど、選考対策の役に立ちそうなことはもちろん、入りたいメガベンチャーの事業内容や業務内容も聞いておきましょう。
どういう働き方やどういう業務をしているかが分かると、入社した後のイメージが具体的になります。イメージが具体的だとどういうふうに会社に貢献できるのかや、志望理由にも深みが出て、他の就活生と差別化できて選考を突破しやすいのです。
とはいえ、身近にメガベンチャーに入社した先輩がいない人もいるでしょう。
そういうときはOBトークを利用しましょう。

OBトークだと、自分の大学以外のOBを探して訪問可能です。メーカーや金融機関含めOBトークでしか出会えない社会人もたくさんいます。
社会人は全員本人確認済みで、運営会社が24時間パトロールしているので安心して利用できます。また、音声機能が付いているので顔出し無しでの訪問も可能です。
オンラインでの音声イベントで社会人の本音が聞けるので、効率的に情報収集したい人に特におすすめです。
最後に|ベンチャーの向き不向きはしっかり確認しよう
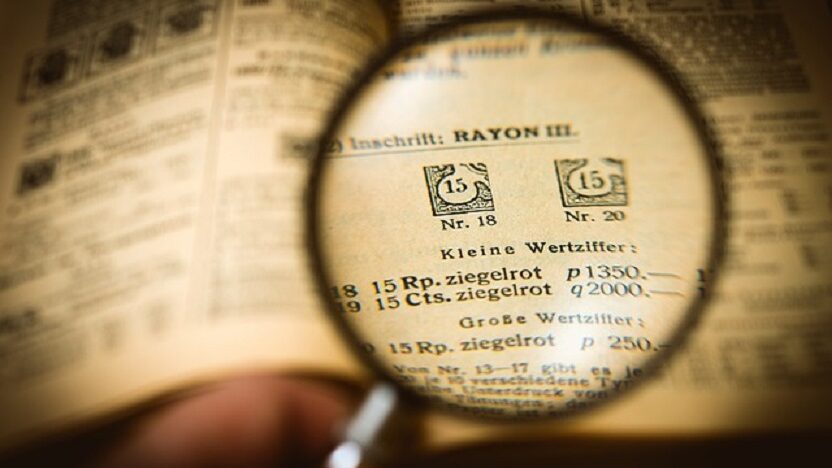
それではこの記事の内容をまとめます。
- 実はベンチャーよりも大企業の方が成長できる
- ベンチャー企業は向き不向きがある
- ほとんどの人にはメガベンチャーがおすすめ
もしこの記事を読んでも自分がベンチャーに向いているかどうかが分からない人は、就活エージェントに相談してみましょう。
自分のことを正確に理解できている就活生なんてほとんどいません。素直に他人の力を借りたほうがスムーズに就活を進められますし、失敗確率も下げることができます。
一瞬にしてあなたのモヤモヤがとれるかもしれませんよ。
- あなたに合った企業を的確に紹介 ⇒ JobSpring Agent
- どんな仕事をやりたいか明確にしたい ⇒ irodasSALON
- 早く内定を獲得したい ⇒ キャリセン
- エンジニア志望 ⇒ レバテックルーキー
- 丁寧なカウンセリング ⇒ キャリアチケット


